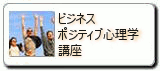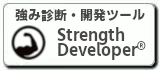<定義>
M・セリグマンの幸せに対する考え方であり、楽しみの人生、充実の人生、意味のある人生、周りの人を大事にする人生の4つを示した。発展中の理論で変化している。
<概要>
・Pleasant Life=楽しみの人生
多くの楽しみを持ち、その楽しみをより楽しめるために努力する。
楽しいこと・快楽、富(家・車・昇給)・娯楽・レジャーなどがこれにあたる。挑戦をしたいと思ったことに挑戦し、自分を忘れて懸命に打ち込んでいて没入してしまう。時間を忘れてしまうほど夢中になっているときに充実感を感じる。
・Meaningful Life=意味のある人生
意味とは自らの使命や行動が、自分だけのためにとどまらず、ほかの人のために役立っているという貢献感を反映したものである。利他の精神とも呼ばれるし、相互協力の考え方の原点にもなる。人が意図的に行動するには動機付けが必要だが、その動機付けの根源を提供する考え方でもある。生きる意味・仕事の意味・業務や活動の意味など、自分が何に貢献できるかを問いかけたもので、その意味の持ち方によりしあわせ観は大きく違ってくる。
・Social Life=周りの人を大事にする人生
人は一人では生きられないと言われる。人にとっていちばんつらいもののひとつが孤独である。仲間の認めあい・思いやりが大事である。この人間関係の充実が幸福感に大きく貢献している。人とのポジティブな関わり合いが、困難を乗り越えるための大きな原動力になったり、自分を元気づける源になったりする。
セリグマンは、さらに考え方を変化させて、2010年には主観的満足度の考えに追加して新しい表記で示している。PERMAである。ポジティブ感情(Positive Emotions)、エンゲージメント (Engagement)、 関係性(Relationships)、 意味と目的(Meaning and purpose)そして達成(Accomplishments)と言っている。
「実証」が進むにつれ、どんどん進化していくがポジティブ心理学である。まだ若い学問であるからこれからも新しい実証が進むと新たな学説が出てくることであろう。楽しみな分野である。